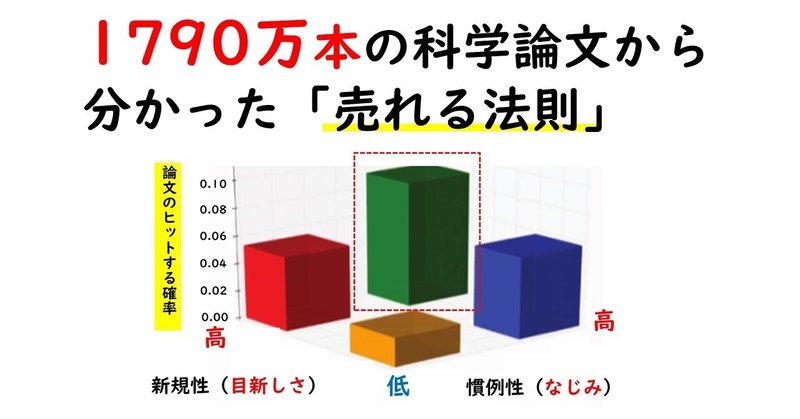
1790万本の科学論文から分かった「ヒットするための法則」とは?お約束+冒険で人は動く!
いよいよ夏休みの時期ですね。
思い出すのは「通知表」です。
あなたはどうでしたか?
あまり楽しい思い出がないのはお互いさまです。
でも、社会に出ると毎日が
「通知表」みたいなものですよね。
さて、ここでちょっとしたクイズです。
学生ならば「テストの点」が、
社会人であれば「売上・利益」が
通知表の対象になります。
では、その真ん中のイメージがある
学者の世界では、何が対象になるのでしょうか?
1. 10億ドルの価値を生む学者の通知表
有力な答えは、こちらです。
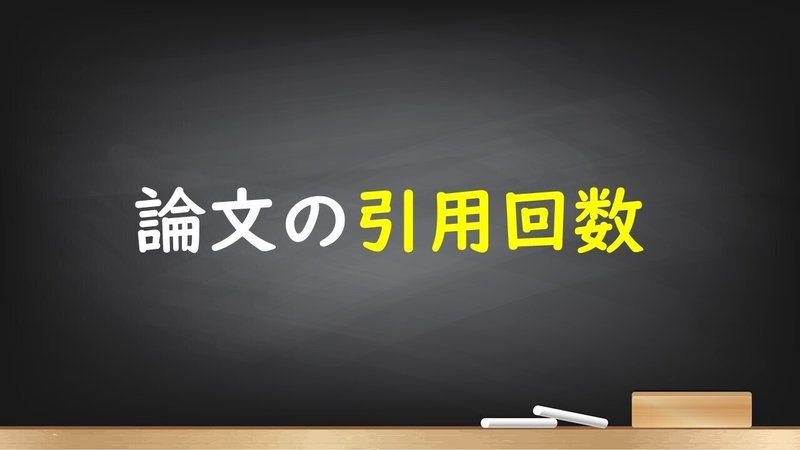
学問の世界では、「新発見」が求められます。
でもそう言い切るからには、
その分野の過去の研究を
しっかり抑えている必要があります。
だからこそ、その分野において
その後の研究の土台となり必ず引用される
論文を出せた場合は、学者の通信簿に
「A」がつくのです。
いわば後に続く人たちへの影響力が
最も評価の軸になっているのです。
物理学の観点から成功法則を追求した
アルバート=ラズロ・バラバシは
さらに踏み込んだ発言をしています。

現在のアメリカでは、科学論文が
1回引用されることで10億ドル分
(約1,100億5,940万円)の研究費に
相当する影響を後世に残すと試算されています。
すごいですよね。
では、どんな論文が
引用されやすいのでしょうか?
すなわち「売れ筋」の論文なんてものが
存在するのでしょうか?
2. 1790万本の論文を調べてわかった「売れる」科学論文の極意
この点を徹底的に追求したのが
ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学の
ブライアン・ウジー教授らの研究チームです。
彼らは、なんと全科学分野にわたる
【1,790万】本もの論文を解析しました。
そして、論文の引用率上位5%に入る
「売れ筋」論文の特徴を調査したのです。
後の研究に影響を与えるくらいですから
斬新なインパクトがあります(新規性)。
しかし、斬新さをうたう以上は、
それまでの既存の研究を
すべてふまえている必要があります(慣例性)。
すなわち目を引く「冒険」と
おなじみの「定番」のバランスが
鍵となっているようです。
そこで研究チームは、
対象論文が引用している
過去の論文にも解析を広げ、
実に【1億2,200万】にも及ぶ
引用パターンを調べました。
まるで森の根っこをすべて数えるような
頭の下がる研究の末に、研究チームは
1つの普遍的な法則を見出しました。
次の考察をごらんください。
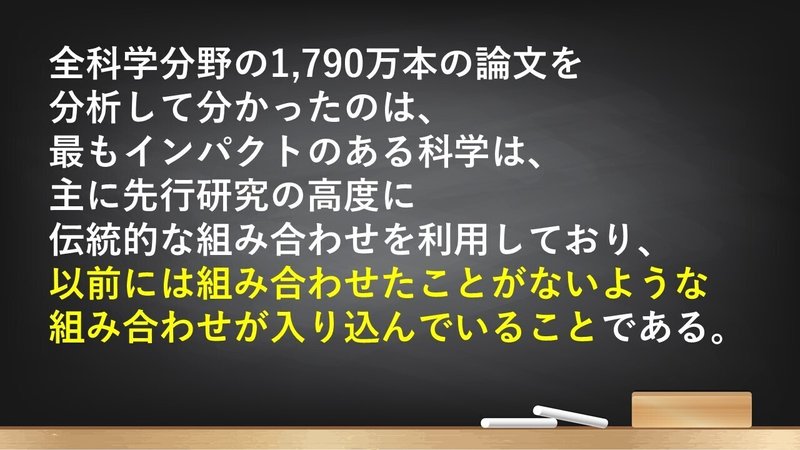
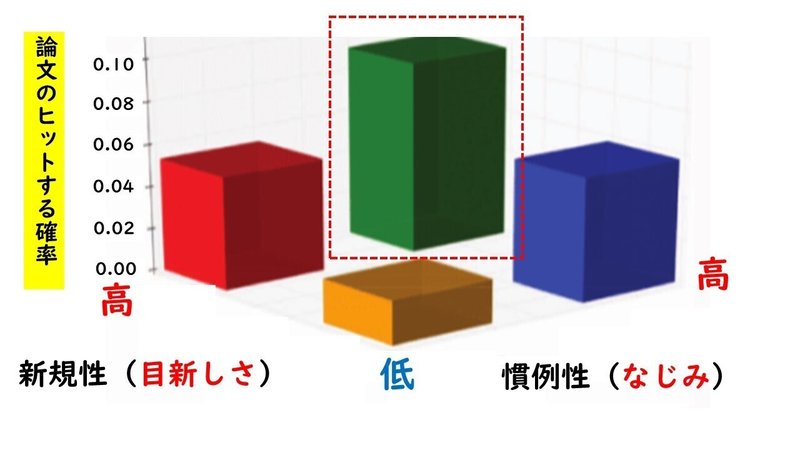
▲ 下記論文より引用 翻訳・加工は投稿者
つまり、しっかり過去のお約束・定番を
ふまえつつ、その組み合わせ方の角度で
斬新さを示していたのです!
ちなみに「斬新性」の部分については
3人以上の著者が書いた論文の方が、
単独の著者の論文よりも【約37.7%】も
割合が大きかったといいます。
複数の視点から入ることで、
浮かぶ組み合わせの幅が広がるのでしょう。
自分勝手でもなく、かといって
模倣やコピーでもない
境目のアプローチが最も大きな
影響力をもちます。
ぜひ、あなたの分野でも活用してみてください。
本日もお読みいただき
ありがとうございました。
ヴォルテックスLINEチャンネル、始動
はじめましての方も
すでに望月俊孝の
公式LINEやFB、メルマガに
ご登録いただいている方も必見!
毎日更新おすすめ記事
最新イベント情報
不定期Lineライブ配信!
ご登録は【10秒】で完了です
【登録後、プレゼントをお届け】
参考論文
参考文献(P.125~129)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

